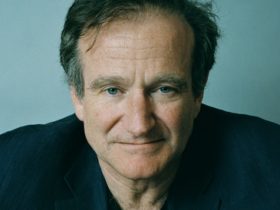- Home
- うつ病に効く食事・食材
- バナナでうつ回復?効果・副作用は?【うつ病に効く食事・食材】
バナナでうつ回復?効果・副作用は?【うつ病に効く食事・食材】

トリプトファンだけではなく、マグネシウム、ビタミンB6も含まれているバナナ
バナナはうつに効果があるといわれているフルーツです。
その理由は、精神を安定させ、睡眠作用があるセロトニンという成分の原料となる、トリプトファンという物質がバナナには豊富に含まれているからです。
トリプトファンとは、大豆製品や乳製品、ナッツ類等の様々な食物中のタンパク質に含まれており、元々は牛乳から発見された必須アミノ酸のひとつです。
食物から摂取されたトリプトファンは、肝臓や腎臓で分解されて、エネルギー源として利用されます。その後、脳に運ばれるとセロトニンを、ナイアシン、ビタミンB6、マグネシウムとともに生成しますが、このセロトニンが不足してしまうと、睡眠障害、うつ状態、不安感等が発生する原因となります。
そのため、脳内のトリプトファン濃度が高くなるとセロトニンが増えることから、トリプトファンは鎮静剤や催眠剤としての効能が期待されています。
実際にトリプトファンを使用して、ヨーロッパ等で行われたうつ病の治験においては、既にその有効性が実証済みとなっています。
トリプトファンは、普通の食事においては微小な量しか含まれていません。そのため、特に他の必須アミノ酸と比較しても、特に不足しやすいアミノ酸となっています。
体内に入ったトリプトファンは、まず脳に運ばれます。
その際、ナイアシン、マグネシウム、ビタミンB6などとともにセロトニンという鎮痛・催眠・精神安定効果のある神経伝達物質を作りますが、欧米ではこのセロトニンの研究が盛んであり、天然の睡眠剤、もしくは若返りの薬として広く知られています。セロトニンは脳の松果体において、メラトニンというホルモンになります。
このメラトニンが加齢を遅らせる若返りの薬として注目を浴びたこともあり、また、このメラトニンは免疫系に働きかける作用もあるため、心臓病や抗がん作用に効果があるとされています。
このような効能を持つセロトニンの量が低下すると、睡眠障害、うつ状態、漠然とした不安感等を引き起こしてしまいますが、セロトニン自体は口から直接摂取できず、食事の中で摂取したものを体内で合成しないと生成できません。そのため、セロトニンの摂取には、その原料となるトリプトファンををいかに摂取するかということが非常に重要となります。
バナナには、このトリプトファンだけではなく、マグネシウム、ビタミンB6も含まれています。
そのため、バナナはうつに効果のある3つの成分を同時に摂取することのできる、優れたフルーツであるといえます。
ただ、バナナに含まれるトリプトファンの量は100g当たり10mgとなっています。
これは、ご飯と比較すると約1/9、牛乳と比較すると約1/4の量であるため、普段の食事のほうがトリプトファンの摂取量が多いということがよくあるようです。
また、うつ病の症状改善のために推奨されているトリプトファンの摂取量は1000mg/日のため、バナナ1本では1%程度しか摂取できないことになります。
しかしながら、バナナにはビタミンB6が豊富に含まれています。
うつ病の症状改善のために推奨されているビタミンB6の1回の食事での摂取量は0.35mgで、バナナ1本には約0.34mg含まれているため、1本食べれば推奨の摂取量をほとんど補えるほど豊富となっています。
ビタミンB6自体にも、疲労を軽減し睡眠を促す作用があります。
そのため、これだけでもバナナはうつ病の改善に効果的なフルーツであるといえるでしょう。